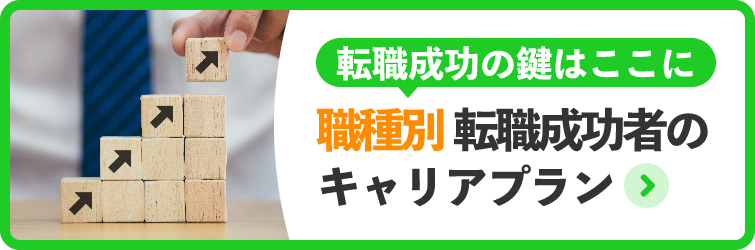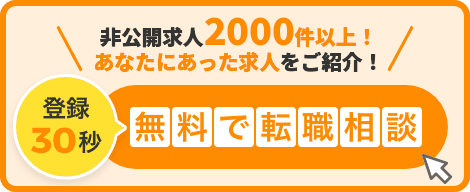SESとSIerの違いを徹底解説!それぞれの特徴やメリット・デメリットもご紹介

IT業界の仕事について調べていくと、「SES」と「SIer」という言葉を目にすることが多いかと思います。また、エンジニアとして働いている人にも聞き馴染みのある言葉の一つです。しかし、両者の特徴や違いについてしっかりと把握していない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
この記事では、SESとSIerの特徴や違い、それぞれのメリット・デメリットや将来性などについて解説をしていますので、ぜひともご確認ください。
Contents
SESとは?

SESとはSystem Engineering Serviceの略称で、IT業界でのシステム開発や運用、保守業務などにおいて、クライアントにエンジニアの労働力・技術力を提供するサービスのことです。
SESの働き方としては、SESを利用したクライアント先にエンジニアが赴き業務をおこなう「客先常駐」という形が一般的なものとなり、クライアント事業でのエンジニア不足を補うために利用されるものとなります。また、SES契約を事業の中心にしている企業のことをSES企業といい、それらの企業はエンジニアの労働力を提供することで報酬を得ています。
SESの特徴
SESの最大の特徴は「準委任契約」であることです。しかし、「準委任契約にはなっているものの、クライアント先に派遣されて仕事をしているのだから、派遣契約と変わらないのではないか?」などと感じる方もいらっしゃると思います。
準委任契約と派遣契約の違いは指揮命令権がクライアント企業にあるか否かとなっており、準委任契約ではエンジニアが所属している企業、派遣契約では派遣先のクライアント企業に指揮命令権があります。
そのため、クライアント企業がSES契約で派遣されてきたエンジニアに業務遂行や労働時間についての指示や管理をおこなうことはできません。
SIerとは
SIerとは、「エスアイアー」と読み、クライアントのITシステムのコンサルティング・企画・設計・開発・運用などをおこなう企業のことです。「System Integration(システムインテグレーション)」の頭文字SIにer「〜をおこなう人」という意味でSIerと呼ばれている和製英語です。
SIerは、クライアントからITシステムの開発業務を請け負い、成果物の完成・納品の責任を負う「請負契約」が一般的です。パソコンなどで利用するシステム開発がしたくても、システム開発部などを自社で設けていない企業が多いため、日本では特にSIerが利用される傾向があります。しかし、近年は国のDX推進も相まって、IT企業以外でも自社でシステム開発をおこなう気運が高まってきています。
SIerの特徴
SIer企業の特徴は、大手・中堅・零細と、SIerのなかにさまざまな規模の企業が含まれることになるかと思います。上述した「ITゼネコン」は仕事のピラミッド構造を表すものとなり、大手SIerが受託したクライアントのシステムを完成させるまでに、複数の企業が関わることを意味します。大手や中堅のSIerが上流工程を担当し、零細SIerが下流工程を担当することが多くなっており、同じSIerという枠組みでも業務内容が異なってきます。
また、1次請けから下請けに仕事が流れている間に中間マージンを抜かれてしまうため、零細SIerは激務薄給となってしまう場合もあり、「IT土方」という言葉も存在します。
SIerの種類
SIerには、「外資系」「ユーザー系」「メーカー系」「独立系」の4種類があり、それぞれに特徴も異なります。SIerについてはまとめている記事がありますので、SIerの種類と合わせてご確認ください。
関連記事:SI(システムインテグレーション)とは?
SESとSIerの違い
契約の種類が異なる
SESは準委任契約、SIerは請負契約という違いがあります。双方の契約はともに業務の指揮命令権はありませんが、SESは成果物の完成・納品責任がなく、SIerは成果物の完成・納品責任がある契約です。
提供しているサービスが異なる
SESはエンジニアの労働力や技術力を提供するサービスであるのに対してSIerは、成果物を納品するサービスです。
利用する企業が異なる
SESを利用する企業は、自社で何らかのITシステムを開発している場合が多く、不足しているリソースを補うために利用する場合が多く、SIerを利用する企業は、自社でITシステムを開発していない企業が多く、そのため成果物の納品を求めている場合が多いです。
SESのメリットとデメリット
SESのメリットとデメリットをお伝えします。
メリット
メリットとして、就職のしやすさがあげられます。
慢性的に人材が不足しているIT業界では、人材不足を補うためにSESを利用する企業が多くあります。一方、サービスを提供する企業は、経験豊富なエンジニアを多く揃えたいところですが、やはり慢性的な人材不足の傾向にあり、未経験に近い状態でも採用する傾向があります。そのため、未経験に近い状態からIT業界への就職を考えている人でも比較的就職しやすい、ということができます。現場で働くことができれば、幅広いスキルを身に付けたり、業務経験を積んだり、いくつも現場を経験したり、場合によっては大手企業の案件にアサインすることもできるかもしれません。人脈を広げていくことも可能でしょう。
デメリット
SESを利用する企業は、派遣されてきたエンジニアに対して指揮命令権がないことから、派遣されてきたエンジニアにミスマッチがあった場合は、すぐに切られることになります。そのため、スキルやビジネススキルがないとアサインできる案件が限られてきます。アサインした案件に当たり外れを感じることが多くなり、似たような案件にアサインさせられたり、スキルが伸びないといったことを感じることもあるかもしれません。
SIerのメリットとデメリット
SIerのメリットとデメリットをお伝えします。
メリット
SIerの就職には、多くのメリットがあります。SIer系の企業がメインにおこなう開発は、業務システムや基幹システムの開発ですが、DX推進により、案件が豊富にある状態が続いています。そのため、大手だけなく下請けのSIer系の企業でも十分な受注量が確保されやすく、好業績が期待されることから、社員として安定的な年収が期待できます。また、SIerは、システム開発の上流工程を担当するため、上流工程に必要なスキルやコミュニケーションスキルだけでなく、決裁権を持つ人物など重要な人物との人脈などを形成することも可能です。キャリアアップとして、プロジェクトマネージャーやITコンサルタントなどへの転向以外にも、独立を考える際にも、そうしたスキルや人脈は役立つかもしれません。
デメリット
多重下請け構造になっているため、ブラックな環境で働かされることも少なくありません。多重下請けであることから、企業の利益率が下がり、利益率が低いことから、より多くの案件をこなさなければならない状況が考えられます。その場合、収入が低かったり、案件をこなすために過密スケジュールとなる場合が考えられます。
ここまでSESとSIerの違いや、それぞれのメリット、デメリットについて解説してきました。SIerへの転職を迷っている方は、下記の案件を参考にしてみてください。
SESとSIerの将来性
SESとSIerは、業務内容の変化は生じるでしょうが今後も事業を継続していくと考えられます。IT人材の不足傾向が続いていくと予測されていますので、SESのように人材を補強する事業が廃れることは想像しにくいといえます。しかし、ChatGPTなどのAIの台頭でプログラミング作業が代替されてきていますので、エンジニアとして生き残るために、プログラミング以外のスキルや知識が求められる状況になるかもしれません。
SIerに関しては、企業がIT人材を育てる気運が高まっているため、「SIerはなくなるのでは」との情報が見受けられます。しかし、DX推進の手伝いのようにSIerの業務内容にも変化が表れていることや、官公庁などの大規模かつセキュリティの高さを求められる案件が多いという背景から、SIerの仕事がすぐになくなるとは考えづらい状況です。
しかしながら、社会の時勢によって求められるものは変化していきますので、SESとSIerは将来性の高い技術や業界動向がどのようになるかを予測し、対応できる業務範囲を広げていく必要があるでしょう。
まとめ
プログラミングを業務の中心としたい方やプログラミング技術を身に付けたい方、未経験からの転職を考える方はSESのほうが向いているでしょう。それに対してSIerは、企業が受託している仕事にもよりますが、マネジメントや上流階級に携わる機会も多くなっているため、プログラミング以外のスキルも身に付けたい方に向いています。
SESとSIerにはご紹介してきたようなメリットとデメリットがありますが、最終的には自分がどういう仕事をしたいか、そのためにどういった行動をするのかが重要になるかと思います。自分の状況やキャリアプランを考えたうえで情報を集め、最適な選択ができるようにしましょう。
SIerとSESについては下記の記事でも詳しく解説しています。特にSIerへの転職をご検討中の方には参考となる記事になっていますので、ぜひご確認ください。